先日、新宿の 「イリュージョン」 にて 「パトリシア」 の原作者、佐藤さんといくつかのカードトリックを見せ合ったのですが、アルド・コロンビニ氏の 「エレベーター・カード」 について面白い話をされていました。
コロンビニ氏の作品は、マルロー氏の 「ペネトレーション」(いわゆる元祖エレベーターですね!) にいくつかの工夫を凝らしてあり、最後にオチとして 「A,2,3を合計すると?」 ……要は3枚のカードが、1枚の「6」のカードに変化してしまうという流れなのですが、佐藤さんが上記のようなフレーズで観客に問いかけると、平気で 「5!」 と答える方が多く、佐藤さんの方が驚かされるというのです。
実際 「イリュージョン」 ではお店の子に演じるところを見ていましたが、「5!」 どころか、堂々と 「4!」 と答えられて面食らっておりました。 ^^;
さて、いったいこれはどうしたことなのでしょう?
観客が、たまたま簡単な算数のできない人物だったのでしょうか?
マジックを頭の中でしか考えられない方や、結構実践しているつもりでも観客層が片寄っている方、何事も大抵観客のせいにしてしまう方などにとっては、理解しがたいことかもしれませんが、これって、実は充分起こりえることなのです。
「観客の正確な思考回路を遮断させる」 という手法は、一見すると奇術家にとってはおなじみの原理なのですが、演者側が意識せずに、かつ必要のないところでこの原理を使ってしまうと、結果的にマイナスの効果が起こってしまいます。
上記の例を一言でいえば、あまりにも質問内容が唐突すぎるのです。
ましてや、たった今目の前で展開している現象に驚いており、観客は一種の思考停止状態であることを忘れてはいけません。
「1足す2足す3は?」 あまりにも答えが明白なため、当たり前にすぐ答えられるだろうという演者側の勝手な思い込みなのです。
あらかじめ算数の話をしておくとか、実際にいくつかの足し算をさせておく、または 「ところで1足す2は?」 「さらに3を足すと?」 など段階をふんで、よりやさしく表現するといった配慮が必要でしょう。
いわゆる 「スリーカード・モンテ」 のように、質問を観客に振らないというやり方もあるでしょうし、無論、あえてうまく答えられないことを想定し、そのケースに合わせたおもしろいセリフを用意しておくというやり方もあるでしょう。
佐藤さんの場合、何度かそーいった目にあったため、そのような問題点を意識することができたわけですが、もしもたった一回だけの経験であったならば、すぐに忘れてしまっていたかもしれません。
例えプロでも(仮に実践の機会が多くても)、この概念のない方にとっては意味がない話なのですが、経験値の積み重ね自体が難しいアマチュアの場合は特に、本当に一回一回の演技と反省を大切にしてほしいと思います。
ところで普段私たちは(少なくとも庄司さんやゆうきは)、このような事例に対してホントに敏感なので、今回の件は興味深くもあり、また、あるていど予測もできる話だったのですが、さすがにお店の子の 「4!」 という答えには驚きました。
念のため理由を聞いてみると、「1,2,3とくれば4かな?」 と、そういった連想であったようです。とにかくいきなり質問を振られて、あわてて 「4!」 と答えてしまったそうで、いわれてみればそれも充分に理解できます。
また、演者にとっては 「Aイコール1」 は当たり前なのですが、これまた一般の方にとっては理解しずらいようです。
どうかくれぐれもお気をつけくださいませ。
それにはまず 「実践したときに気が付く」 ようにならないと ……ね!
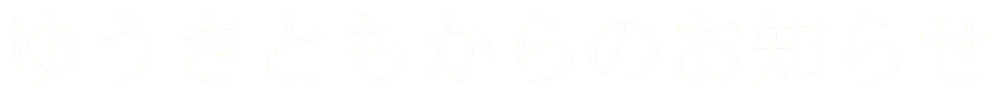
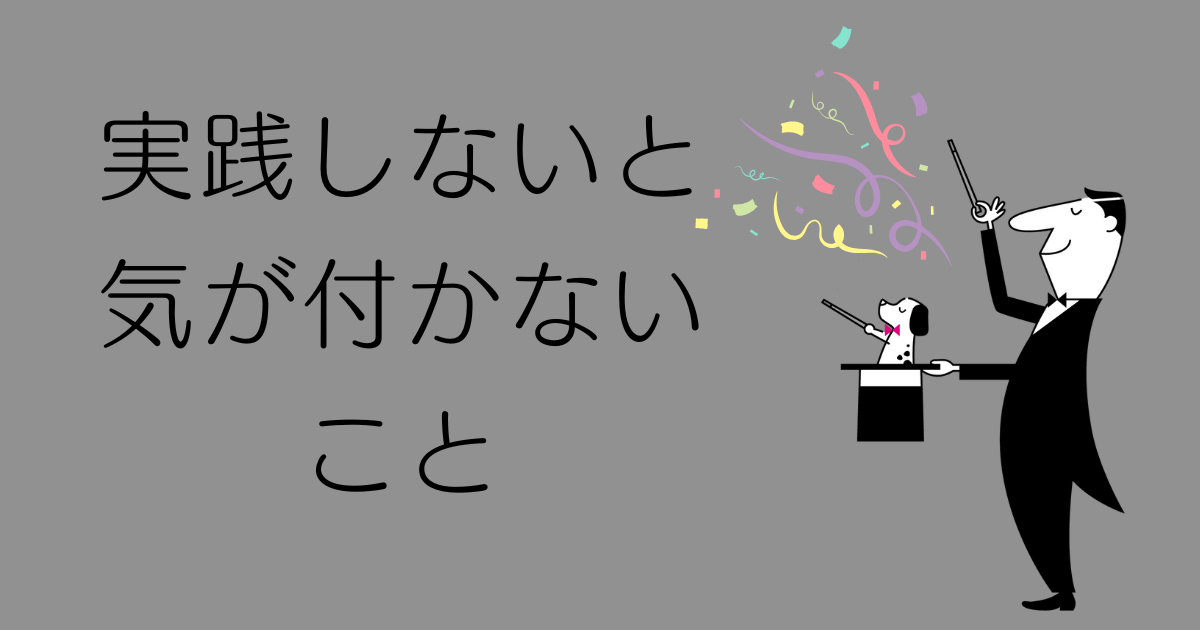
コメント